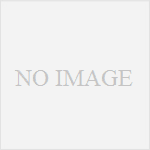「分かってるでしょう」
目の前で言うトニは困り顔で、頬杖をついている。
「フワだって考えなしじゃないわ。あなたがフワの立場でも、きっとそうしたはずよ」
諭すような声色に、すぐに返事は出なかった。イジビーはかわりにため息を一つ吐く。
「……分かっていますよ」
返答を聞くと、トニが呆れたように頬を膨らませる。
トニへ返せる言葉は何も思い付かなかった。彼女の言うことは、今回ばかりはぐうの音も出ないほどに正しいのだ。
食事時をとっくに過ぎた酒場からはほとんどの顔見知りが出払い、店内はがらんと空いている。店員すらもいないカウンターへ、いつものように食事を漁りに席を立つトニを、イジビーはコップの水滴を拭きながら眺めた。
――背負った弓は休日くらい下ろせばいいのに。この場に無関係なその言葉は、口から出さずに飲み込む。肝心の休日にまで付き合わせている原因は自分だ。
「あ、封開いてないお酒があるわ。飲む?」
「あなたの酒に付き合えと? 御冗談を。水で結構です」
「つれないんだから」
控えめなサイズの酒瓶を片手に戻ってくる。閑話休題、とばかりにグラスに注いで、再びイジビーに視線を戻した。
「彼に謝る気は?」
「……まあ、先刻みたいに噛みつくような真似は、もうしませんけど」
向かいのグラスの氷がアルコールに馴染み、からりと涼しげな音を立てた。イジビーのところまで少し強めの、しかし甘酸っぱそうな香りが漂ってくる。
「ならいいけど。その顔、まだまだフワへの文句ありそうじゃないの」
「不服も不服ですよ。腹立たしいんですよ、私は」
「腹立たしい?」
「そうですよ。死角の矢から庇ってやったって……まるで私が! 矢ァなんぞで機能不全に陥るみたいに! こう、弱いみたいに!」
「えー……」
トニはため息のような相槌をしてから、グラスの酒をぐいと煽った。悩んでいる時にこう飲めれば、さぞ気持ちが良いだろうか――酒を嗜まないイジビーからしてみると、未知の領域だ。
「フワに比べたら。私もイジビーも吹けば飛ぶようなものだけどさあ」
「絶対舐めてますよ、あいつ」
「まあ……フワなら腕の二本や三本……飛んでも平気そうな感じはあるけどさ?」じゃなくて、とトニが言葉を続ける。「弱いと思ってるんじゃなくて……ほらほら。致命傷じゃなくたって痛くないわけじゃないんだから」
「そこは、私もフワも同じでしょうが」
「んふふ。心配?」
「……ちょっとうるさいです」
「図星じゃん」
「うるさいです」
「もう。意固地」
トニは笑って、グラスの酒を飲み干した。それ以上は聞かないでおいてやる、というしたり顔だ。開封した酒瓶をイジビーに押しやる。
「これ、フワにあげてちょうだいな。あんま飲まないだろうけど、まあ一杯くらいはいいでしょ」
「何のおつもりで?」
「晩ご飯にはちゃんと揃って顔出してよ、ってこと」
「……善処はします」
はいはい、とあしらったような返答を残して、トニは席を離れる。迷いのない足音と鳴るドアベル以降、酒場には閑散とした静寂が戻った。
しばらくぶりのため息をまた一つ。軽やかとは程遠いものの、当初のそれとは色を変えた気がする。
誰もいない酒場で、イジビーは一人居住まいを正した。
短編小説「深夜酒」
 創作
創作