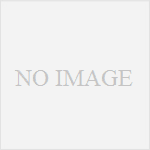猫って不思議だ。暗闇でもこちらを見つけて、いつの間に忍び寄ってくるのだから。
ベンチに腰掛けた男は、同じくベンチに居座っている猫に目をやった。こいつは何が面白いのか、かれこれ数分は男をじっと見つめている。
男は夜の公園を散歩中、落し物を見つけた。なんてことはなくふらりと寄っただけの散策で、偶然キーホルダーを拾ったのだ。いかにも神社で購入したような形の、鈴が付いたお守り。くすんだ土に塗れたせいか、鈴らしくない濁った音が鳴る。
この汚らしい物をどうしてしまおうか、交番に届けるのも面倒だ、いいやなぜそこまで面倒を見なければ――そんなことで唸りつつ、ベンチに座った。そこに登場したのはこのまん丸の瞳だ。一体どこに隠れていたのか、ものの数秒でひょこりと顔を出して座面に座る。その後、飽きずに男を見つめているのだった。
男の様子には構わず、にゃあ、とひと鳴き。まるで気さくな友人から会釈されたみたいだ、と男は思った。久々に会った友人と世間話をするような――なあ、何してるんだいこんな夜中に。散歩はいいがこのご時世、深夜に不審な男は通報されるぜ。いくらお前が近所の小学生とも仲が良い、好青年だとしてもさ。
男は猫について、気まぐれな生物だという印象を持っている。少なくとも、こんな風に警戒心なく近付いてはこないだろう。どうやらこいつは変わり者らしい。
「こんばんは」
子どもをあやすように、声をかける。
猫は首を傾げた。それはそうだな、と男は独りごちた。動物に話しかけて通じるわけがないのだ。ペットを可愛がっている人間にとっては通じるものなのかもしれないが、男は動物を飼ったことも、まともに触れ合った経験もなかった。言葉で語り合える相手だとは見なしていない。
声をかけてみたのはただの気まぐれだ。だが、何となくまだ話し続けようという気分になった。猫が気まぐれでないなら、人間が気まぐれになるのだ。
「何してるんだ」
にゃあ。
「腹でも減ってるのか」
耳をぴくりと動かす。
「何も持ってないよ」
にゃー。
「……」
男は足を組み直した。馬鹿馬鹿しい、と思わず表情に出たが、それを咎める猫ではない。
早くも我に返る。自分は一体何をやっているのか。こんな夜、誰もいない場所で、猫に話しかけて。一人で喋っていれば、それこそ通報される。
それでも、この場を勝手に立ち去ることは友人を無視して立ち去るようで、何となくためらわれた。ひと呼吸の間に迷いを消化して、代わりに拾い物のキーホルダーを置く。
「あげる。じゃあな、お休み」
猫は窺うように、目の前のキーホルダーと男とを交互に見やる。男はようやく腰を上げた。
何のことはない無駄な時間だったが、いい暇潰しにはなったかもしれない。そんなことを内心に留めて立ち去る人影を、猫はきょとんと見送るのみだ。
*
「おはようございます!」
登校の時間帯、この町は賑やかだ。家を出ればすぐそこから指定通学路であり、ゴミ出しをする男に対しても無邪気な挨拶が飛んでくる。テンプレートのように繰り返される挨拶に、「近所のお兄さん」としてにこやかに返す。
「おはようございます」
ただそれも、誰もいないときにまでにこやかでいる必要はない。挨拶が済めば仏頂面だ。気を抜いた表情で、いつものゴミ捨て場に袋を放った。
いつの間に児童が来ていたのか、背後からまたひとつ挨拶が投げかけられる。
「おはようございます!」
「おはようございます」
通り過ぎる人影へ挨拶を返してから、思い出したように会釈をする。登校の波に飲まれていてはキリがない、早く家に戻ろう――そう思いつつ顔を上げた視界に入るのは、鮮やかなランドセル。そこから音が鳴る。
鈴らしくない、濁った音がひとつ。
「……あれ?」
男は立ち止まり、惚けた声を出す。その間にも子どもは道を渡ってゆき、離れていくその姿を見送るしかなかった。
今の自分はまるで、道路の横断までを親切に見守っているようだ。そんな風に、いやに俯瞰した感想を抱くのだった。
数年前、小説投稿サイトに出したものです。